|

|
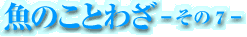
---ハモ---
海とその生物にまつわる諺や格言についてお話しましょう。
今回のテーマは鱧(ハモ=ウナギ目アナゴ科ハモ属)です。魚へんに豊かと書く鱧は、関西の夏の味覚を代表する食材の一つです。
体は細長くウナギ型をしており、どう猛で鋭い歯を有し、魚、エビ、カニ、イカ、タコと何でも食する大食漢でもあります。
主に、本州中部以南に分布しております。
|
|
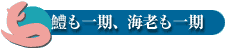
ハモとエビは、同じ海の動物であるのに、随分と形や生活様式が違う。それでも、それぞれの一生を過ごす。
人の生涯も上下・貧富・愚賢の差があっても、等しく一生を終える。宜しく達観すべしの教え〈俳諧毛吹草〉。
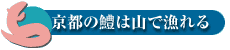
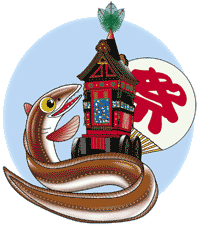 ハモは京(関西)の魚。 ハモは京(関西)の魚。
ハモは生活力が旺盛な魚で、水を離れても長時間生きているので、山国の京都で珍重されてきた。それに、輸送の途中で逃げ出し路傍を這いずり回るハモもいたようで、「山の芋変じて鰻となる」のような、こんな言葉が生まれた。
ハモは歯が鋭く“食む”が訛った呼び名である。
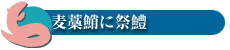
麦の穂が出る初夏の頃のタコと祇園祭の頃のハモ、ということで、どちらも関西(京)を代表する魚。
ハモは梅雨の水を飲んで旨くなり、大き過ぎず卵を抱いた「つの字鱧」を最上の味とするが、ハモは小骨の多い魚。
これを「骨切り十年」の腕で、「一寸を二十四に包丁する」骨切りをして、小骨が舌触りせず、しかも包丁の刃が皮に達しないように料理する。
二階堂清風編著「釣りと魚のことわざ辞典」東京堂出版より転載。
| 水温と海藻類の成長<2> |
海生研では、海藻類に関する野外や室内における様々な試験研究を行っています。
海藻類の多くは浅海域の海底や物体に固着して成長するため、地域的な環境変化の影響を受けやすい生物の一つと考えられます。
図は食用になる岩ノリであるウップルイノリの室内試験結果の一部です。幼芽期の葉状体を20日間培養した結果、15~20℃に成長の適温範囲があることが分かりました。
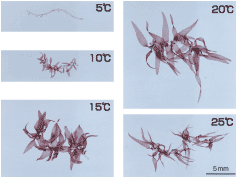
|
|